まずは、以下の物語を読んでみよう。
「窮屈サイズの報酬」
ある男が靴屋に入ると、向こうから優しそうな店員が近づいてきた。
「何かお探しでしょうか?」
「ショーウインドウにあるような靴が欲しいのですが」
「かしこまりました。そうですね、お探しのサイズは・・・・四十一号、ですね?」
「いや、三十一号をお願いします」
「あのう、お客様、私この道二十年になりますが、お客様のサイズは四十一号かと。ひょっとすると四十号かもしれませんが、三十九号ではございません」
「三十九号をお願いします」
「申し訳ございませんが、足のサイズを測らせて頂いてよろしいでしょうか?」
「どうぞご自由に。でも私は三十九号の靴が欲しい」
定員は引き出しを探って、サイズを測るのに使うあの奇妙な器具を取り出し男の足を測ると、満足げに言い放った。
「ほら、私のいったとおり、四十一号です」
「あのですね、誰がその靴を買うんですか、あなた?それとも私?」
「お客様です」
「よろしい、それでは三十九号の靴を持ってきて貰えますか」
店員はしぶしぶ三十九号の靴をとりにいった。
そしてその男は靴べらを使って何度も何度も、馬鹿げた姿勢を取ってみたり悪戦苦闘して、やっと男は靴の中に足をはめ込んだ。
うめき唸りながら難儀そうに何歩か歩く。
「大丈夫です。これを貰います」
店員は三十九号の靴の中で圧迫されている指を想像するだけで、自分の足が痛くなるほどだった。
男は店を出て、仕事先のある三つ先の通りまで歩いた。男は銀行の窓口係りだった。
午後四時半、靴に足をねじ込んでから六時間以上がたったころ、男の表情はゆがみ、充血した目からはおびただしい涙がこぼれてきた。隣の窓口から見ていた同僚は気が気でなかった。
「どうした?体調でも悪いのか?」
「いや、靴のせいだ」
「靴がどうかしたのか?」
「きついんだ、二サイズ小さい靴だから」
「足は痛くないのか?」
「痛くて死にそうだよ」
「いったいどういうことなんだ?」
「それはね」
唾をごくりと飲み込んで、男は話し始めた。
「私は生きていても大きな満足感を得られない。実際、最近は気分の優れるときがほとんどない」
「それで?」
「今靴がきつくて死にそうだ。ものすごく苦しいよ、本当に・・・・・・でもこれがあと二時間もすれば、家について靴を脱ぐ。なあ、そのときの喜びを想像できるか?最高だよ、おい、最高だ」
情報源:ホルへ・ブカイ「薯」童話セラピー
この話を読んでどう感じ取っただろうか?狂っているみたいに感じた人も多かったはずだ。我々は苦労をすれば報われるという考え方があり、苦労をしないで成功した人には批判があるのが一般的だが、本当にその考え方でいいのだろうか。
現代の競争社会が当たり前のように育った私達は、苦労して人より一歩出しぬくことで偉いと感じたり、褒められたりすることで習慣化されてしまった。
しかし、それは勝ち組と負け組みをつくっていくだけではないだろうか。永遠に出口がないラットレースを走っている感じがするのは私だけだろうか。
本来、本当の喜びとは、人を出し抜くことではないはずだ。すべての人が幸せになりたい、そう思っているはずだ。
国、人間どうしの競争という枠組みから、まったく新たな枠組みを考える必要があるのではないだろうか。









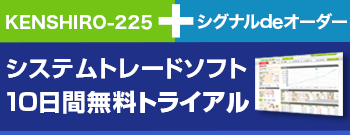


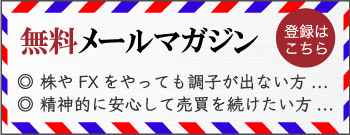






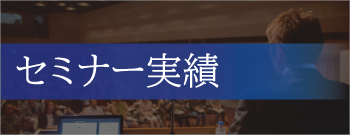





SECRET: 0
PASS:
芥川龍之介も似たようなこと言ってる。
でも芥川的にはラットレースから抜け出すには
自殺しかなかった。
SECRET: 0
PASS:
>coniさん
コメントありがとうございます(笑)
さて、芥川龍之介は、coniさんのおっしゃるとおり自殺をしたと言われていますが、幕末の志士、坂本龍馬は、今のような時代の変わり目に、新しい枠組みをつくることに成功した一人だと私は思っています。
「日本の中で争っている場合出ではない」と日本を一つにまとめたように、今度は世界を一つにまとめる政策を行ってほしいものです。